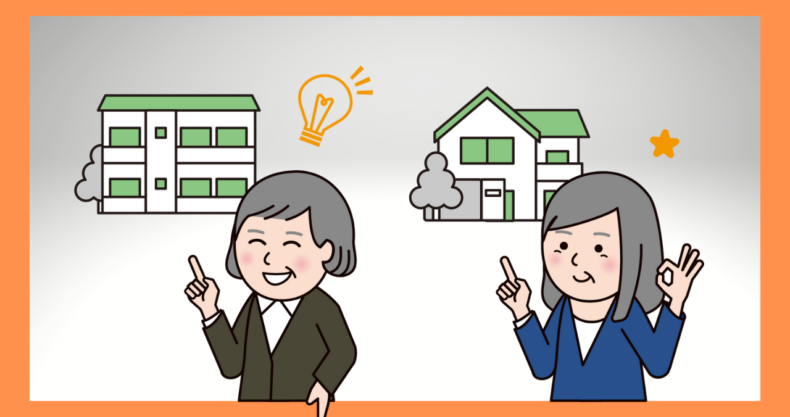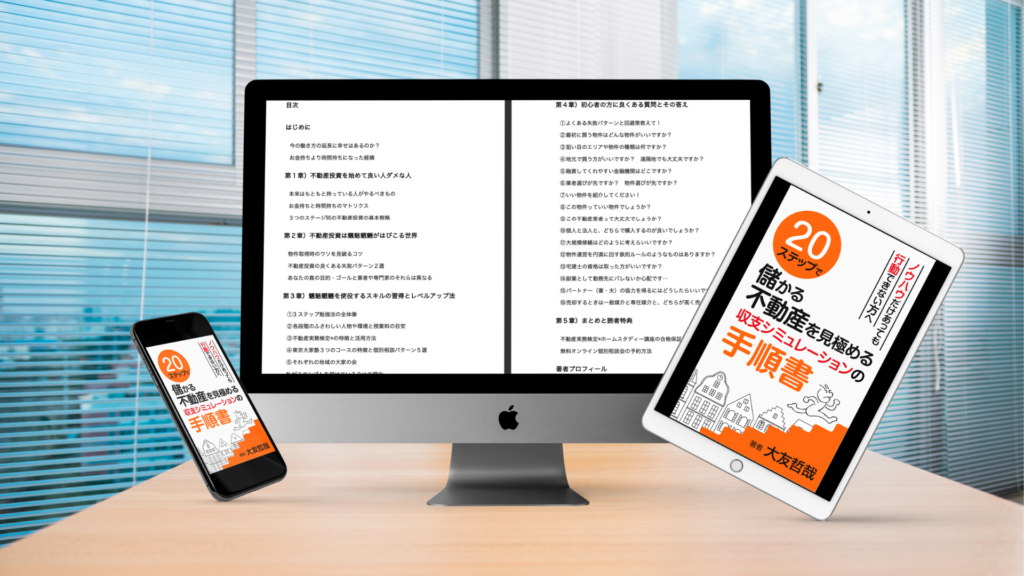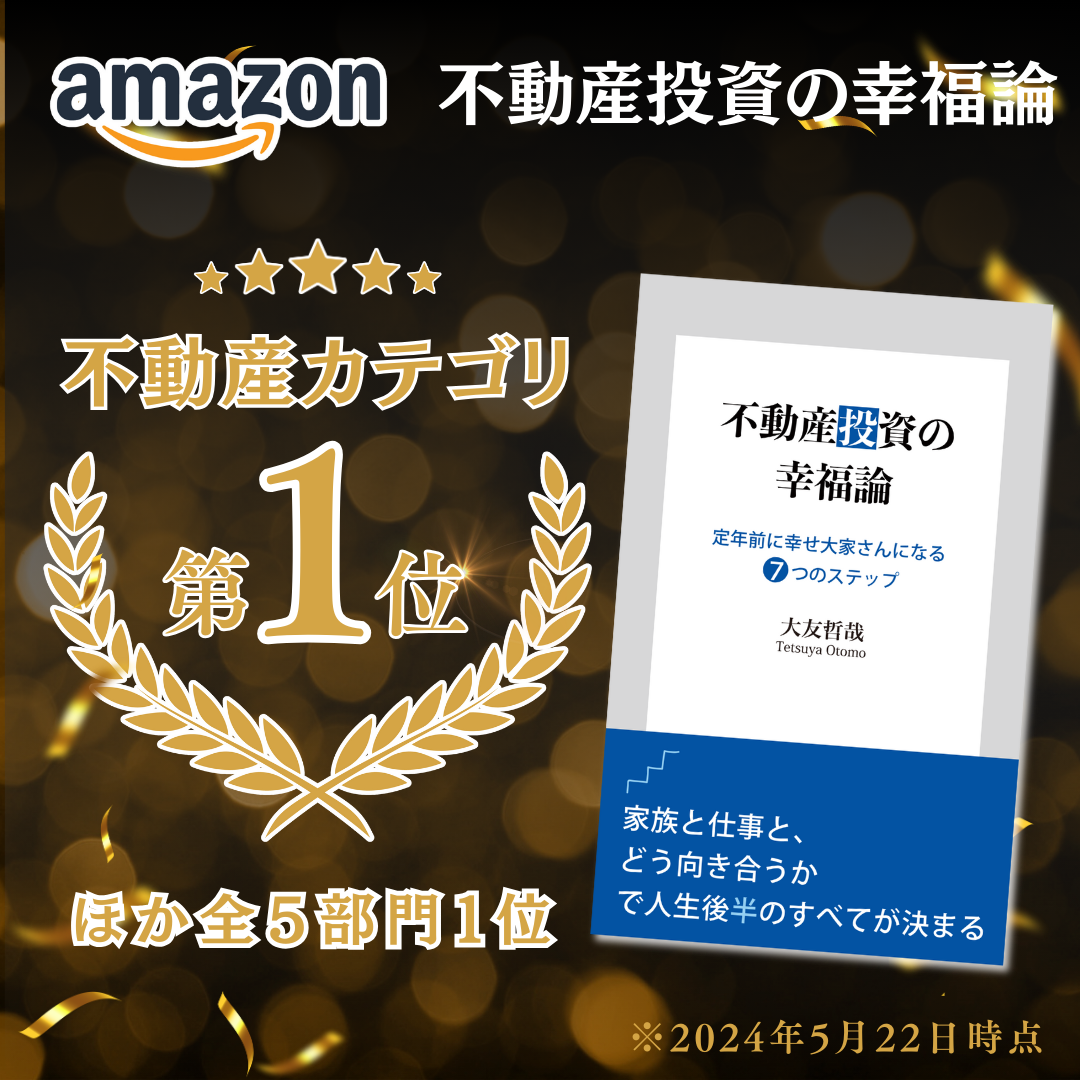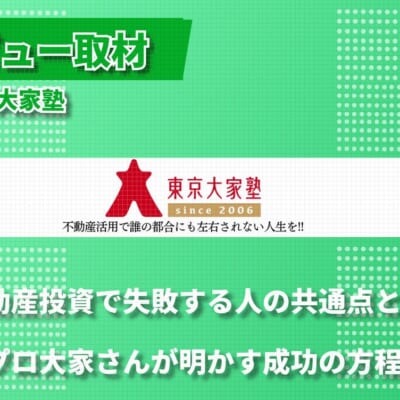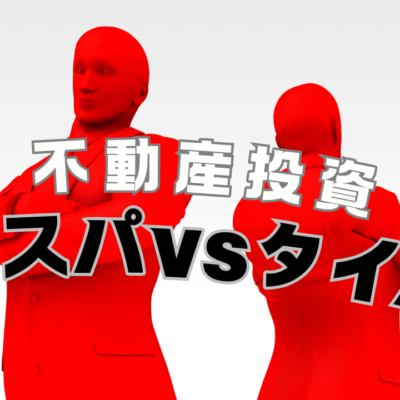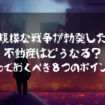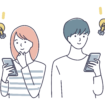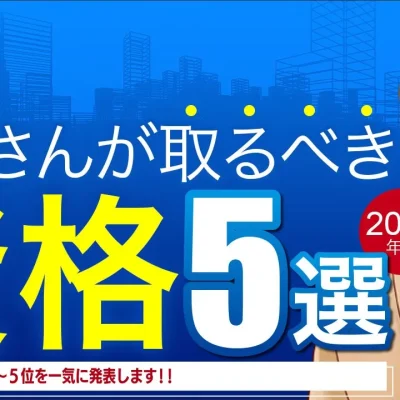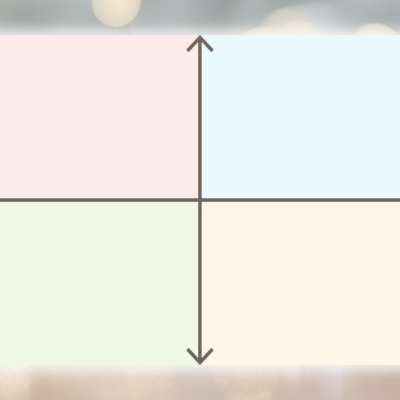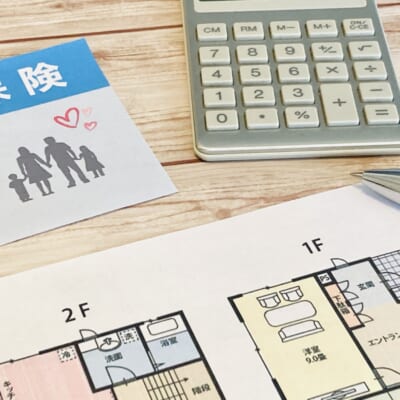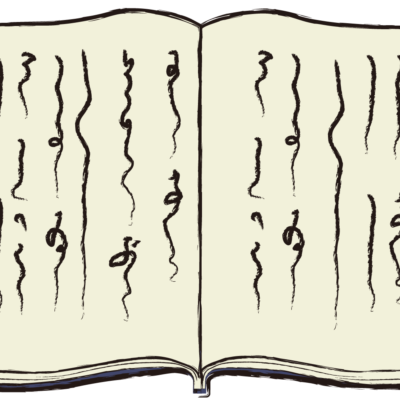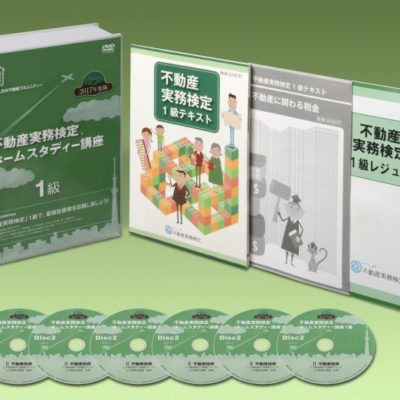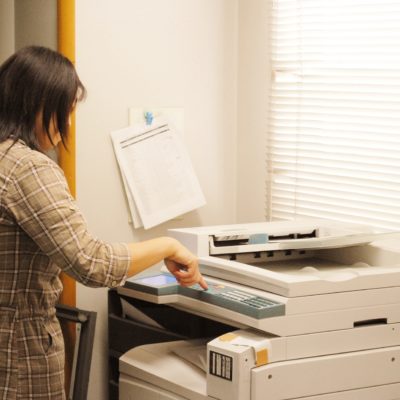最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- 新築一択だった30代会社員。彼がリノベ現地セミナーで気づいた築古物件の新たな可能性とは。 - 2025年6月12日
- 物件評価の基準が定まらないあなたへ。見学会で物件選びの迷いが晴れた理由 - 2025年6月12日
- 売却か、家賃収入UPか。60代大家がセミナーと見学会から学んだ資産価値向上法 - 2025年6月12日
2006年から東京大家塾で毎月研究会を続けている私が、物件が買えない人に共通するパターン3つ解説します。
今回は1つ目。結論はズバリこちら。
投資基準がない
投資基準とは、購入すべき物件の条件のこと。例えば、価格帯・立地・利回り・築年数・構造などなど。
この投資基準が決まっていないと、物件を紹介されたりポータルサイトでめぼしい物件を見つけても、判断できずに迷っていると、ライバルに先を越されて買い逃します。
少なくとも、興味はあることを仲介会社等には伝えるべきなのです。そうすれば、後からライバルが出てきたら教えてくれますし(急かされるとも言います笑)動向も教えてくれます。
良い投資基準・悪い投資基準
良い投資基準とは、物件情報を見て1分で判断できるものです。
ですので、曖昧だったり範囲が広すぎたりして、物件情報を見てから価格や家賃の相場を調べるようでは1分では無理なので悪い投資基準となります。
もちろん、ここで言う判断とは「買う・買わない」ではありません。1万円2万円みたいな商品ではないのですから。
具体的には、詳細な資料請求をするだとか、現地に行くだとか、つまり次の段階に進むのか、進まないのかの判断です。
そして仲介会社には「基本的に買いたいと思うが、銀行や税理士などに確認を取りたいことがあるので、少し待ってほしい。」と連絡します。場合によっては、買付証明(購入申込書)も出します。
逆に、投資基準に合わないときは、どのあたりが合わないのかを仲介会社に伝えます。
投資基準があると仲介会社が味方になる
このように、仲介会社などに即、フィードバックできるお客様は、仲介会社の営業担当者としては助かるものです。なぜなら無駄がないからです。
彼らが嫌がるのは、買う買う言う割には返事が遅かったり、購入判断が曖昧だったり、矛盾した判断をしてきたりするお客様です。紹介するのに時間や手間が掛かっています。そして彼らは成功報酬です。時間を無駄にすることを激しく嫌います。2度3度と続けてしまうと、次から物件情報を送ろうとは思わなくなるでしょう。
判断は買う・買わないの2択ではない
このように、ポイントは「買う・買わない」の2択の判断基準ではなく、70点を超える方どうかの「どちらかと言えば買いたいが・・・」の状態で仲介会社に連絡することなのです。
あなたはには、そのように判断するための投資基準はありますでしょうか? もし、ないようなら投資基準、つくってみましょう。
もし、分かっちゃいるけど、なかなかつくれない・・・という場合は、投資スタイルという投資基準をつくるための指針や方針をつくるのが先となります。投資スタイルについて、次回、少し紹介します。
この記事をレビュー
更にコメント投稿で電子書籍プレゼント
電子書籍はePub形式なので各種、電子書籍アプリ1で読めます。PDF版もありますので印刷もできます。
では、下記よりコメント投稿よろしくお願いします。